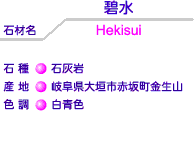 |
 |
 |
|||
| 鮮やかな白に、淡い青色のぼかし模様が入っているのが特徴です。小さな摂理上の面がキラリと光る半結晶化したような組織も見られます。全山が古生代の石灰岩から成る岐阜県大垣市赤坂の金生山(標高217メートル)から採れる石材の一つです。大垣市街の北西にあるこの山は、「化石の宝庫」として世界的に知られ、二億年以上も昔のフズリナ、貝類などの化石が大量に見つかります。石灰岩に含まれる化石などの成分の違いから、地層により黒系、白系、紅系など、色と石種が無数に異なります。その中でも「碧水」は、美しい色と輝きを持った代表的な石材の一つといえます。 | |||||
| 「碧水」は、「青色に深く澄んだ水」(広辞苑)という意味です。石材の「碧水」は、鮮やかな白色の石肌の中に、淡いブルーの模様が流れるように入っています。ところどころにはキラリと光る輝きも見えます。それは、西美濃にそびえる秀麗な山、伊吹山の懐から流れ出る清流を連想させます。「碧水」のネーミングは、実に石材の持つ美しさを言い得た命名といえそうです。 金生山で採れる石灰岩は、地名をとって「赤坂大理石」と呼ばれ、全国的に知られています。そのうち、「碧水」は、「美濃黒」「美濃霞」と並ぶ代表的な石材です。 |
|||||
| 金生山は、二億五千万年~三億五千万年の古生代末期に誕生した山です。かつて海にいた巻貝、二枚貝などの貝類、サンゴやウミユリなどの殻、骨格が、海底に堆積し、化石を豊富に含む石灰岩が、古生代ペルム紀(二畳紀)の海中でつくられました。その石灰岩が、海底の地殻変動によって隆起し、小高い山になりました。それが、金生山です。そのため、化石が豊富に採れる山として世界的にも知られ、「古生代研究のメッカ」として有名になりました。 東西1.1キロ、南北2.2キロ、標高217メートル。全山が石灰岩でできています。石灰岩は、焼けば石灰、磨けば大理石となります。赤坂では、明治から昭和初期にかけて、自然の賜物ともいうべき石材を生かした大理石細工が盛んとなり、明治時代の多い時は250人を数えました。しかし、金生山は戦後の高度成長のもと、セメントの材料となる産業用石灰の製造のために大規模な石灰岩の採石が行われました。その結果、今では元の三分の一の大きさにまで山肌を削られ、古生代に誕生したときの山の姿を大きく変えています。 |
|||||