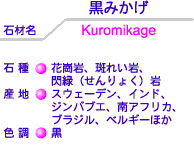 |
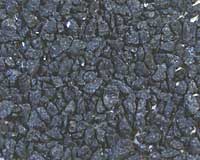 |
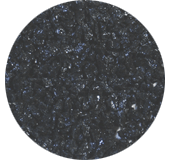 |
|||
| 「黒みかげ」は、閃緑岩や斑れい岩の通称というのが一般的です。また、黒雲母を主成分とする花こう岩もこの名前で呼ばれることがあります。地下のマグマが冷えて固まった火成岩の仲間で、石質は硬く、加工性はよくありません。耐久性、耐磨耗性、風化には強い反面、耐火性は低いとされています。 この石の仲間で、福島県のほぼ中央、黒石山(896m)で採掘されている「浮金(うきがね)石」は、その希少性から有名です。黒褐色の斑れい岩で、名前の通り、黒地の中に金や白色の斑が混じり、それが浮き出るが如く絹糸状に光を放つのが特徴です。 |
|||||
| 黒みかげは、文字通り、「黒いみかげ石」という意味で、そう呼ばれています。「みかげ」の由来は、兵庫県六甲山のふもとの御影地方から産出された花崗岩の石材を「御影石」と呼んだことから始まりました。現在は、その意味から大きく拡がって、各地の花崗岩をはじめ、閃緑岩、斑れい岩などの無色および有色鉱物を「御影石」と呼んでいます。そして、本家の御影地方の御影石は「本御影石(ほんみかげいし)」の名前で呼ばれています。 同じ「黒みかげ」でも、花崗岩もあれば、南アフリカ産の斑れい岩もあります。なぜこのような混同が起こるのかというと、岩石の種類は組織・成分・などを元に分類されますが、石材として取り扱う場合は色や模様に重点を置いて、異なる岩石の種類でも同じ石材名で取り扱っています。 ちなみに、外国産のものは、それぞれ国名や産地名などを冠して、ジンバブエブラック(ジンバブエ)、ベルファースト(南アフリカ)、アンデスブラック(ブラジル)、ベルジアンブラック(ベルギー)といった名前がついています。 |
|||||
| 花崗岩、閃緑岩、斑レイ岩は、火成岩の中の深成岩に属する岩石です。マグマが地表に噴出することなく、地下の深い所で徐々に冷えて固まった岩石です。そのため、地面の強い圧力を受けて、徐々に雲母や長石といった色々な鉱物の結晶が現れます。6000万年〜5000万年前の新生代にできた岩石です。 花崗岩は、1つ1つの大きな鉱物の結晶が集まってできた石です。マグマが冷却すると、地下の深い所ではマグマが熱 を外に逃がしにくいので、ゆっくりと長い時間をかけて冷却・固化し、結晶の1つ1つがほぼ同じ大きさにまで成長して「等粒状組織」をつくりました 斑れい岩は、深成岩のうちでも、SiO2成分(ガラスのようなもの)が少ない塩基性岩で、主に斜長石や輝石といった鉱物からできています。白く透明な鉱物が斜長石で、黒色はほ輝石です。斑れい岩の組織は、比較的小さな鉱物が集まっていることが分かります。このことから、マグマから岩石へと固まるまでにかけた時間は、結晶の大きな花崗岩と比べて、短い時間で岩石になったものと考えられています。 |
|||||