 |
 |
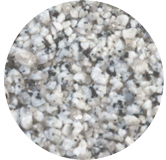 |
|||
| 「稲田みかげ」は、「白御影」とも呼ばれるように、その際立った白さが特徴です。国内で産出するみかげ石の中では最も白いとされています。主成分は、雲母、長石、石英の3種。そのうち、60%強を占める白色の長石が、稲田石の色調を決定づけています。石質は硬く優美で、磨き上がりの光沢も優れ、加工性に富んでいます。耐久性、耐磨耗性がよく、風化に強いがのが特長です。 「稲田みかげ」は、100年以上の長い歴史と伝統を持っています。明治37年、東京市電の軌道敷石に供給されるようになって、一躍良質材として全国に知れ渡り、需要が増大しました。 堅牢なうえ地肌が白く美しいため、石段、石垣、灯籠、敷石、鳥居、墓石、外柵、玄関回りなどの建築資材として幅広く使われています。主な建物としては、東京都千代田区の最高裁判所はじめ、帝国劇場、日本勧業銀行本店、茨城県立歴史館など、日本を代表する建築物に用いられています。最高裁の公式サイトにも、「内堀通りの三宅坂辺りに白い花崗岩の外壁が目を引く建物があります。そこが最高裁判所です」と紹介されています。 |
|||||
| 花こう岩は一般に「御影(みかげ)石」と呼ばれます。その起源は、兵庫県六甲山のふもとの御影地方から産出された石材を「御影石」と呼んだことから始まったようです。現在では「〜みかげ石」と、各産地の地名をかぶせて区別するようになり、茨城県笠間市稲田にある通称・石切山脈と呼ばれている地区を中心に、東西8Ɠ、南北6Ɠにわたる山地一帯で産出することから、「稲田みかげ」と名付けられました。 | |||||
| 花こう岩は、火成岩の中の深成岩に属する岩石です。マグマが地表に噴出することなく、地下の深い所で徐々に冷えて固まった岩石で、1つ1つの大きな鉱物の結晶が集まってできた石です。マグマが冷却すると、 その中から徐々に鉱物の結晶が現れます。地下の深い所ではマグマが熱 を外に逃がしにくいので、ゆっくりと長い時間をかけて冷却・固化し、結晶の1つ1つがほぼ同じ大きさにまで成長して組織をつくりました。こ のようにしてできた岩石が、花こう岩です。6000万年〜5000万年前の新生代にできた岩石です。 | |||||